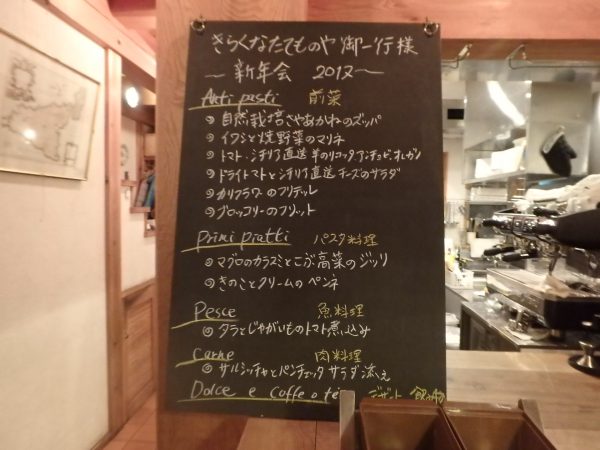2017年1月4日
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
皆さまはどんなお正月を
お過ごしになりましたか。
私はといえば、
正月に体調を崩したこともあり、
テレビでラグビーを観ながら、
寝込んでいました。
ゆっくりラグビーが観れるのも、
ゆっくり寝込むことができるのも、
正月ならでは、ですね。
明日から仕事始めなのですが、
体調のほうは
うまい具合に間に合いそうなので、
大丈夫です。
さて今年の年賀状は、
以下の写真に、
「素材の生命をいただく」
という言葉を添えました。
黄土を横に引き摺って
掻き落とした土壁と、
五十嵐さんが
達磨窯で焼いた
一枚一枚表情の違う敷瓦。
職人たちの手による
土という素材を
様々な手法で生かした
表現です。
土は無機質で、
それ自体恒久的に存在するものですが、
職人が手塩にかけて育て上げたものは、
まるで生命が吹き込まれたようです。
事実まるで命あるもののように、
日によって見え方が変わり、
あるいは少しずつ
時の経過に伴って、
表情が変化していきます。
さて、話は変わりますが、
昨年末の大掃除で
アルミサッシの網戸を
洗ったところ、
十数年前とほぼ同じと思えるほど
きれいになりました。
よかったよかった、と思う一方で、
これは木の建具では
ありえないことだと思いました。
アルミサッシに限らず、
現代の建築を見てみると、
外部に使われる素材の多くは、
洗い流したら簡単に元に戻る、
つまり「永遠」を追求した
素材に囲まれているように思います。
そういえば昨年末に
誰かと何度か、
現代的な住宅が、
同じ素材に統一されて
ずらりと並んでいるまちなみを
たまに見受けますが、
それが美しいと感じるかどうか、
という議論になりました。
そこで聞こえてきた意見の多くは、
あまり美しいとは感じない、
というものでした。
一方で例えば、
日本の伝統的な建物が
立ち並ぶまちなみは、
木や土といった素材で
統一されていて、
その統一感がむしろ
美しいと感じさせるのですが、
現代の素材は
どうしてそう思わせて
くれないのだろうか。
ちょうどそんな疑問を
抱いていたところなのですが、
アルミサッシの網戸を洗ったあと、
自分の中でなんとなく
答えを得たような気がしました。
それは、
私たちはいつかは朽ち、
いつかは消えゆく
命あるものを美しいと感じる
本能があるのではないか、
ということです。
例えば一般論として、
美しいと感じる度合いは、
如何に均整の取れたマネキンも、
命ある生身の人間には
かなわないのと同じです。
この現代は技術が発達して、
ほぼ「永遠」の素材や工法が可能となり、
その集積として今の住宅は、
おそらく耐久性が
格段に上がっているのだと思います。
それはそれで、
いい面もあるのだと思うのですが、
正直ワクワクしない、
というのが本音です。
そこで
本能に素直な私は(笑)、
その本能にしたがい、
ワクワクすると感じる
‘生きている’素材の命をいただき、
‘生きている’職人の手で作り、
心地よい、美しいと思う場作りを
今年も試み続けていきたいと思います。
それでは今年一年、
よろしくお願いいたします。